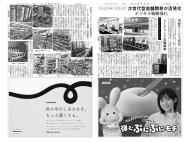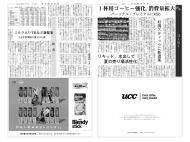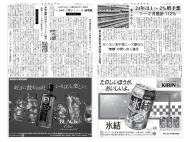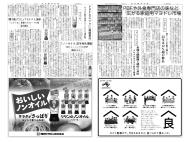食料醸界新聞は、毎号、トレンドに合わせた特集・企画をしています。
※スクロールして下さい
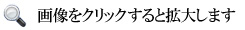
※スクロールして下さい
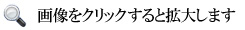
【 総数:2031件(141〜154件を表示) 】 前の14件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 次の14件
ビール類(2024年4月8日号)
23年のビール4社の販売数量は、ビール類合計で前年比99%と推定され、ビールは107%、発泡酒(発泡酒②除く)は112%、新ジャンル(発泡酒②)は85%で着地。ビールは業務用の回復基調や酒税改正による減税などもあり好調。各社はビール強化に一段と力を入れており、この流れは今年も継続。1〜2月累計でビール類は105%。ビールが117%と2ケタ増で市場を牽引。発泡酒①は136%、新ジャンル(発泡酒②)は81%で推移する。24年の市場はビール類計で96〜98%から前年並みと推定されており、ビールは104%ほどと引き続き伸長が見込まれている。年初から活発な商品施策で、スタンダードビールに新ブランドが登場、リニューアルも相次ぐ。これからGWを挟んで前半戦の勝負どころ、成(…)
バター・マーガリン(2024年4月8日号)
家庭用バター・マーガリンは、それぞれ年間2度の値上げを克服、底堅い需要を示している。マーガリンは、22年度(4〜3月)2度の値上げを経て23年度は前年超え(金額ベース、以下同)で、経済性の高い大箱を中心に動きは好調だ。J‐オイルミルズの家庭用マーガリン事業終了を受けて、今春以降の売り場活性化策、「ラーマ」ユーザーの動向が注目される。乳等を主原料とする食品ではチューブタイプが好調を維持。この1年で売価が2割近くアップしたバターは物量減を小幅に抑えており、今年は物量でのキャッチアップに期待がかかる。
23年度の家庭用マーガリン市場は前年超え、別の調査データでは106〜107%水準もあり、年間を通じ順調に推移。値上げラッシュともいえる食(…)
23年度の家庭用マーガリン市場は前年超え、別の調査データでは106〜107%水準もあり、年間を通じ順調に推移。値上げラッシュともいえる食(…)
缶詰・びん詰(2024年4月8日号)
缶詰・びん詰の市場は主力である水産缶詰のサバ、サンマなど主要魚種が記録的な不漁が続き、原料確保自体が困難になっている状況。ツナ缶原料のカツオ・マグロ相場は一時の高騰からは下降したが魚価は高水準。コロナ禍で定着した家飲みに適したつまみ缶、まだパイは小さいがアウトドア向けの商品も需要拡大を見込む。即食性の訴求をはじめ、災害大国としての防災備蓄食や素材としてのアレンジレシピ提案など消費喚起策と、原料価格を含めあらゆるコストが上昇し、値上げが追い付いていないことも課題。
サンマは漁獲量が過去最低水準が続いているため、国内生産量(日本缶詰びん詰レトルト食品協会調べ)は22年が3353t(593千箱)、10年前の13年(…)
サンマは漁獲量が過去最低水準が続いているため、国内生産量(日本缶詰びん詰レトルト食品協会調べ)は22年が3353t(593千箱)、10年前の13年(…)
乾物(2024年4月1日号)
乾物は、コロナ禍での内食化を契機に需要が伸長し、その収束後も引き続き安定推移。一方で、原料となる農・海産物の状況を見ると、跡継ぎ不足や廃業などに起因する生産者の減少傾向が年々顕著となり、それに伴い生産量も不足。結果、原料相場は高値安定で推移し、さらに上昇する気配もあることや、人件費や物流費、光熱費なども上昇するなど、製造コストの上昇が圧迫。自助努力ではその吸収はこれ以上は困難として、海苔業界等では今年も再値上げを発表。こうしたなかでも乾物は、栄養豊富で、トッピング用途にも使用でき、長期保存も可能など、優れた機能を一層訴求。課題とされる若年世代への浸透や開拓などにも意欲的に取り組む姿勢が見られる。
ふりかけ・お茶漬けの素(2024年4月1日号)
ふりかけ市場は節約志向が続いていることもあり追い風が続いている。食品類全般の値上げも今年に入りやや落ち着いてきているものの、実質賃金が物価上昇に追いついていないため、大きな流れは変わらない。22年秋に登場した、わかめを使用した食感系のふりかけが新カテゴリーとして存在感を強め、わかめ以外も含めて「食感系」ふりかけが増えてきた。弁当需要の大幅回復でおむすび・混ぜ込み・ソフトの領域強化も目立っている。お茶漬けの素は永谷園の『めざまし茶づけ』プロモーションの効果もあり、小さな子どもがいる世帯の需要を掘り起こし、その流れに他社も乗っかっている格好。
揚げ物関連商材(2024年3月28日号)
油ハネや使用後の油の処理、調理技術の難しさなどから、家庭内での調理の機会が減少傾向をたどってきた、から揚げや天ぷらなどの揚げ物メニュー。ここ数年は、原料相場の高騰や円安により食用油や小麦粉の価格改定が相次いだこともあり、その傾向が加速した。スーパーマーケットの惣菜やコンビニのカウンター商品などの人気メニューとして揚げ物が浸透し、家庭で揚げたてを楽しむ機会はめっきり減ってしまっている。そこでメーカー各社は、それぞれの技術力を活かし、新たな機能を持ったクッキングオイルや揚げ物用ミックスを展開するとともに、新たな調理法や食シーンの提案も推進。植物油の健康イメージも定着してきており、こうした施策が次第に生活者に浸透し始めていて、おいしく、(…)
みそ(2024年3月28日号)
大手メーカーを中心に春夏新商品が出揃った。今年は、みその新商品は少ないが、従来のカテゴリーとは違う新たな需要創造を狙った商品開発が目立つ。いずれも個性あふれる商材で、今後の展開は未知数なものが多いが、チャレンジングであり、流通筋の関心を集める。また、4月より、無添加表示の厳格化によるパッケージ変更に伴い、商品を大幅リニューアルする動きもあり、このあたり、市場でどういった反応があるのかも注目されそうだ。
最大手のマルコメは、発酵×植物性ミルクという新ジャンルの「プラス糀 米糀ミルク」を開発。甘酒とは違う、新たな糀飲料により、これまでとは違う層にもアプローチ。流通筋の関心も高く、話題を呼ぶ。「プラス糀(…)
最大手のマルコメは、発酵×植物性ミルクという新ジャンルの「プラス糀 米糀ミルク」を開発。甘酒とは違う、新たな糀飲料により、これまでとは違う層にもアプローチ。流通筋の関心も高く、話題を呼ぶ。「プラス糀(…)
ヨーグルト(2024年3月25日号)
長らく静かだったヨーグルト売り場に、今春は活況が戻りそうだ。新型コロナで制約のあった1年前とは異なり、今年は満を持して開発した新商品が多く、話題性も豊かで、春需を盛り上げる売り場づくりが進む。これまで続々と登場してきた機能性表示食品が、飽和状態とささやかれるなか、新たな価値提供に挑む商品開発が目立つ。高付加価値、高単価商品が少なくなく2023年度に続き、連続前年超えに期待がかかる。
2023年度(4〜3月)のヨーグルト市場は、金額ベースで前年比103〜104%、概ね4700億円前後(消費者購入ベース)と推計され、久々の前年超えとなりそうだ。ただ、生産物量ベースでは5年連続前年割れとなっている。牛乳乳製品(…)
2023年度(4〜3月)のヨーグルト市場は、金額ベースで前年比103〜104%、概ね4700億円前後(消費者購入ベース)と推計され、久々の前年超えとなりそうだ。ただ、生産物量ベースでは5年連続前年割れとなっている。牛乳乳製品(…)
CVS(2024年3月25日号)
コンビニエンスストア各社は現在好調で、既存店ベースの売り上げが前年同月を上回っている。一方、新規出店のペースは鈍化し、店舗数の純増は減少傾向にある。そんな中、セブン‐イレブン・ジャパンやローソンは次世代型店舗の実験を開始。デジタル戦略を強化すると同時に新たな需要を創出するため、商品・サービスの領域を拡げる取り組みを進めている。時代の変化に対応してきたCVSチェーンの運営は転換を迫られている。コロナ禍で生活スタイルが変化し、新たな生活様式に合わせたCVSの展開が求められ、店舗形態も見直しが必要不可欠となっている。宅配サービスの導入は加速し、ローソンはウーバーイーツなどフードデリバリーサービス業者と組んで導入店舗数を増やしている。セブンは本(…)
冷凍食品(2024年3月21日号)
24年度の家庭用冷凍食品市場は3〜5%増が予想されている。外食回帰や節約志向、再三の価格改定などの逆風はあるものの、共働きや単身世帯の増加もあり“タイパ”は重視されている。コロナ禍を経験して間口は大きく拡大し、美味しさ及び即食・簡便食として認知が浸透、売場拡大とチャネルの多様化もあり着実な成長を見込む。好調な食卓用だけでなく、弁当用の回復も底上げ要因。個食、ワンプレート、健康などをキーワードに今春もメーカーは商品開発を強化、売場誘引のためテレビCMやデジタル施策など積極的なプロモーション活動も予定している。価格改定により単価はアップしたが、数量の減少から上昇への反転が継続課題。
ニチレイフーズは強化しているパーソナルユースのトレー入り個食麺(…)
ニチレイフーズは強化しているパーソナルユースのトレー入り個食麺(…)
コーヒー・紅茶(2024年03月18日号)
国内の23年コーヒー総消費量は、生豆換算で40万1913t、前年比92.8%と2年ぶりに減少した。原料豆の調達価格が相場の高止まりと円安でさらに上昇し、価格改定を余儀なくされるなど厳しい経営環境が続く。業務用市場は人流回復で活況だが、家庭用市場は巣ごもり消費の反動と節約志向で消費量ベースでは停滞した。金額では復調し、コスト増をある程度カバーできたが、今年は家庭用の消費量回復に向けて、商品価値の向上、新たな提案に注力している。ライフスタイルの変化への対応を強化し、特に1杯個包装のパーソナルユースの製品は、業界の課題でもある若年層の新規ユーザー獲得につながるもの。夏に向けてはアイスコーヒーや、冷水で作れるパウダー、コーヒーバッグなどの提案が活発化している。
低アルRTD(2024年3月14日号)
低アルコールRTD市場(ハイボール含む)は、24年1〜12月の販売数量で前年比1〜2%増と予想されている。23年実績は1〜2%増とみられ、サントリーの推計では1%増の約2億7487万ケース(250ml×24本換算)。22年はコロナ下の家飲みが落ち着き、業務用が回復する状況で、1%程度の減少と僅かだが15年ぶりに実績割れとなったが、23年は活発な人流や夏場の猛暑も寄与して再浮上。24年も引き続き安定成長が見込まれる中で、有力各社からリブランドを含めた主力ブランドへの更なる注力、“無糖”の押し出し強化が打ち出され、食中酒ニーズの高まりを捉えて、新市場を創造する提案型商品の投入も活発。1〜2月は推計112%と順調な滑り出し。昨年10月の酒税改正第2弾で増税の新ジャンル(…)
乾麺(2024年3月14日号)
乾麺は今年も需要堅調。経済性、保存性などにより、コロナ後も引き続き、消費者からの支持を獲得していることが背景にある。一方で、業界関係者が一様に気を揉んでやまないのが人手不足で、高まる需要に対し、十分な供給も危ぶまれるとの声も一部で聞かれる。手延素麺の産地では、人手不足が伝統産業の継続をも脅かしかねない、と話す関係者もいる。安定供給の仕組み作りが業界にとって急務。コロナ禍明けとともに、乾麺の海外輸出も回復傾向。乾麺各社はこの春夏、素麺と冷麦を軸に展開していきながら、今後を見据え、蕎麦、うどん、中華麺などの強化・拡大に乗り出す。
乾麺の価値について、ある手延素麺の産地関係者は「地形や環境をい(…)
乾麺の価値について、ある手延素麺の産地関係者は「地形や環境をい(…)
マヨネーズ・ドレッシング(2024年3月7日号)
家庭用マヨドレ市場では、各社とも主力アイテムの多彩な容量ラインナップを活かし、購入チャネルの多極化や、世帯構成の変化、節約志向の高まりに対応するほか、機能性を持った商品を強化し、コロナのなかで一層高まった健康志向に応えてきた。さらに最近ではプラントベースフード(PBF)や“平飼いたまご”の使用、外食専門店の味の提供など、生活者の多様な価値観と嗜好への対応が進んでいる。なお、全国マヨネーズ・ドレッシング類協会による2023年のドレッシング類生産量は39万8479t(前年比101.0%)。うちマヨネーズ21万3066t(98.0%)、その他半固体状ドレ6万9033t(107.6%)、液状ドレ9万9882t(103.6%)、ドレタイプ調味料1万5894t(98.6%)となった。
和風だしの素(2024年3月4日号)
和風だしの素市場はコロナ後再び緩やかに減少傾向ではあるものの、家庭内での常備率は高く、主力用途である手作りみそ汁には欠かせない基礎調味料のひとつ。みそ汁は手作りから即席へ、メニューによっては白だしや麺つゆが代替調味料となるし、ワンランク上に仕上げるにはだしパックが便利。調理時間がない時は調理済みのスーパー惣菜や冷凍食品の登場頻度も増えてくる。原料高による価格改定が2〜3年の間に複数回あり単価が上昇、ワンサイズ小さい内容量へのシフトも顕著になっている。節約志向が強まっている中でも「プチ贅沢」を味わいたいというニーズに応え、味の素社は新ブランド「休日だし。」を立ち上げ新たな需要開拓に挑戦する。
【 総数:2031件(151〜165件を表示) 】 前の15件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 次の15件