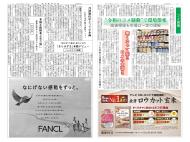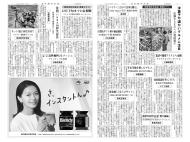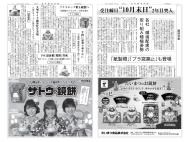食料醸界新聞は、毎号、トレンドに合わせた特集・企画をしています。
※スクロールして下さい
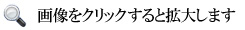
※スクロールして下さい
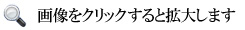
【 総数:2031件(71〜84件を表示) 】 前の14件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 次の14件
コメ流通(2024年11月21日号)
今年は、新米商戦を前に需給バランスが大きく崩れたコメ市場。一時は、店頭からコメが無くなりパニックとなる状況も見られ“令和のコメ騒動”は、業界内外に大きな影響を及ぼした。R6年産が出回り始めても「集荷相場としては依然として高止まったままで推移している」という声も聞かれ、現在もコメ相場は高止まりした状態にある。一方「新米商戦としては厳しく始まったが、10月下旬より動きを取り戻しつつある」とし、直近では、新価格体制が消費者に受け入れられているようす。また、無菌包装米飯を始めとした加工米飯市場は順調に拡大。大型設備投資も活発化しており、さらなる成長が見込まれている。
「“令和のコメ騒動”だ」――。今年8月に発生したコメの需給バランス(…)
「“令和のコメ騒動”だ」――。今年8月に発生したコメの需給バランス(…)
RTDコーヒー(2024年11月18日号)
RTDコーヒー市場は1〜9月で前年比微減とみられ、容器別では缶とボトル缶が減少傾向、パーソナルサイズのPETボトルコーヒーは幅広い世代の飲用層と飲用シーンを取り込み堅調だ。ただPETは10月に価格改定が実施され、販売への影響が注視される。SOT缶は昨年の価格改定が一巡して以降は堅調だが、回復には至っていない。ヘビーユーザー維持へコミュニケーション施策を展開。ボトル缶は、カフェショップ連動のブランドが強い。市場全体の活性化に向けてPETを中心に若年層など新規ユーザーの獲得に各社注力している。
PETコーヒーが主流になってきており、サントリー食品インターナショナル「クラフトボス」とコカ・コーラシステム「ジョージア」が2強を構成。(…)
PETコーヒーが主流になってきており、サントリー食品インターナショナル「クラフトボス」とコカ・コーラシステム「ジョージア」が2強を構成。(…)
包装餅(2024年11月14日号)
コロナ禍以降、改めてその利便性が脚光を浴びて需要が拡大する包装餅市場。今年1〜9月の「包装餅」生産量は4万2635t(前年比6.9%減)。前年実績ではマイナスだが、昨年は生産量が大幅に伸長して1〜12月で前年比4.6%増となっており、反動減を加味すると依然として需要は高止まりしている状況だ。特に、今年は8月に発生した“南海トラフ地震臨時情報”と“コメ不足報道”の影響を受けて「包装餅」にも特需が発生。一時はメーカーの生産がタイトになる状況も見られた。一方「包装餅の家庭内ストックは、恐らく過去例がないほどの状況となっている」という指摘もあり、これからの最需要期にどういった影響があるか注目されている。原料事情については、コメの相場高を受けて非常に厳しい状(…)
白みそ(2024年11月14日号)
これから最需要期に突入する白みそ商戦。関西や中四国では、正月の雑煮に白みそを使う事から、一年で最も白みその需要が増加する。11月の段階では顔見せ的な要素が強いが、12月に入れば、売り場は大きく変化。白味噌の露出が急拡大する。昨年は、コストアップによる価格改定の影響が若干見られた。今年も、コストアップによる厳しい市場環境下にあるが、現状では、価格改定の動きは見られず「昨年、値上げで数量が若干落ち込んだので、今年はポイント販促を加えて拡販に注力。前年実績プラスを計画している」(関西地区スーパー)という声も聞かれ、需要は安定するという見方が多勢だ。ただ、コメの相場高がメーカー各社の収益を圧迫。現状では、企業内努力で吸収しているが、相場は高止(…)
本格焼酎(2024年11月11日号)
本格焼酎は、消費喚起に引き続き最重点で取り組む。炭酸割りやお茶割りなどの飲み方提案や、トレンドの香り系焼酎の訴求強化を推進。コモディティ商品も価格軸でない取り組みで、市場での話題づくりを欠かせない。高付加価値商品の構成比を高めていくことも重要。ユネスコ無形文化遺産に「伝統的酒造り」が12月に登録されるよう、ユネスコ評価機関が11月5日に勧告した嬉しいニュースも飛び込んできた。海外での認知向上、市場開拓にも繋がる話題として、PRする機会を増やしていきたい。
本格焼酎の課税数量は、国税庁の1〜7月で前年比96.1%。1〜9月の日本酒造組合中央会概数は95.1%の23万9036kl(約132万8000石)で推移する(…)
本格焼酎の課税数量は、国税庁の1〜7月で前年比96.1%。1〜9月の日本酒造組合中央会概数は95.1%の23万9036kl(約132万8000石)で推移する(…)
歳暮ギフト(2024年11月7日号)
11月に入り本格的なお歳暮商戦が関東地区百貨店で開始。今年は例年よりも店頭での開催が遅い店舗も多く、各社ともに10月から先行してスタートしているオンラインでの販売を強化し、前回の中元期に販売比率がすでに半分近くにまで成長している百貨店も見られる。クリスマスや新春向けに洋菓子を中心にしたスイーツや鍋物などの温かいグルメを強化し、コロナ禍以降定着している自宅用商品や個別包装、レンジ調理などの簡便商品も引き続き需要を見込む。一方で、昨今の台風やゲリラ豪雨などの影響で果物の入荷遅れや在庫の安定確保が難しく早期で販売を締め切るなど、災害が多くの影響を与えている。厳しい環境の中でもオンラインなど成長するカテゴリーへの注力を行い、売り上げの拡大と若(…)
チェーンストア(2024年10月31日号)
社会構造やライフスタイルをはじめ、世界の潮流さえもコロナ以降に変化が加速し、食品・流通産業はその変化への対応を迫られている。チェーンストア業界でも、コスト上昇と値上げが続くなかでの節約志向の高まり、デジタル化進展の一方で触れ合いを求める消費者心理、地球環境や社会課題への関心が高まっているものの伸びないエシカル消費など、市場は複雑さを増し、多様な価値観が入り乱れている。効率化や標準化を得意とするチェーンストアにとって、多様性は必ずしも得意分野ではない。新たな時代に対応するのは、新たなマネジメント手法やビジネスモデルの構築、さらには将来の成長につながる価値観を獲得することが必要で、それを実現する“人”を如何に育成するのかが最も大切な経営(…)
清酒(2024年10月28日号)
清酒は、例年にも増して話題の多い秋冬商戦で、消費の活性化が期待される。主力ブランドの周年記念が重なり、積極的な販促企画を展開。低アルコールへの対応では、新機軸の商品が関心を集める。高品質で値頃感のある大吟醸のリニューアルも相次ぎ、改めて4合瓶の棚の陣取りに注目。日本酒を炭酸で割る「酒ハイ」の提案も、首都圏の飲食店で成果をみせ、取り組みの広がりに期待である。海外市場の開拓も引き続いての重要課題で、現地でのアクション強化が欠かせない。
清酒の課税数量は、日本酒造組合中央会まとめの1〜8月で前年比96.3%。都道府県別で実績クリアは12地域、構成比で25%を占めており、昨年同期が(…)
清酒の課税数量は、日本酒造組合中央会まとめの1〜8月で前年比96.3%。都道府県別で実績クリアは12地域、構成比で25%を占めており、昨年同期が(…)
マーガリン・スプレッド(2024年10月24日号)
家庭用マーガリン市場は、生活防衛意識の高まりや食パンの好調を背景に上期は金額で前年比100〜101%と堅調に推移した。J‐オイルミルズの家庭用マーガリン事業終了(3月)による「ラーマ」ユーザーの、マーガリン市場からの離反を食い止め、市場の維持・拡大を図ることが課題の一つだったが、雪印メグミルク、明治とも商品強化と増量をはじめとした販促強化による取り込み策が奏功した。引き続きマーガリンの食シーン拡大、ユーザー開拓などに注力し市場活性化に注力している。
マーガリン市場は、前年上期に105%と伸びており、今上期はこの水準を維持した。メーカーの意欲的な施策はもちろんだが、特に9月はコメ不足の影響が顕著で、パン食の増加により消費者購入ベースでは単月で前年比106%と高伸長した。(…)
マーガリン市場は、前年上期に105%と伸びており、今上期はこの水準を維持した。メーカーの意欲的な施策はもちろんだが、特に9月はコメ不足の影響が顕著で、パン食の増加により消費者購入ベースでは単月で前年比106%と高伸長した。(…)
鏡餅(2024年10月21日号)
鏡餅の市場規模は約100億円ほどと推測される。その需要期は12月の限られた期間に集中する。短期間でそれだけの金額を売り上げる商品である事から製販ともに失敗できない貴重なカテゴリーと言える。メーカー各社はこの間、環境配慮の取り組みを進めてきた。そうした中で、今年はサトウ食品が一石を投じ、今年の鏡餅の商品施策として、プラスチック橙を廃止して紙製の橙に変更。小飾りでは橙を固定していたプラキャップも廃止する方針に舵を切った。さらに、化粧箱のプラスチック窓も廃止。アルミ箔を使用した金色の三方から、伝統的な木目調の紙製三方に変更。「トップダウンで決定。お客様にゴミとなるものを極力無くしたいという思いから、業界に先駆けて決断した」(佐藤元社長)と(…)
ワイン(2024年10月17日号)
ワイン市場は、昨年10月の酒税増税や円安による値上げなどもあり、数量ベースでは苦戦が見られた。金額ベースでは、値上げによる販売単価の上昇、昨年世界的に品薄となっていたブルゴーニュワインやシャンパーニュなどの在庫が安定したことで、前年を上回る実績となったメーカーも多くなった。特に中価格帯から高価格帯の商品が伸長しており、カヴァなどシャンパーニュ以外のスパークリングワインの需要も増加傾向にある。日本ワインはワイナリー施設の整備や畑の拡充が進み、クオリティも国内外のコンクールで上位の賞を獲得するなど味わいや品質が高い評価を受ける。円安傾向が改善され、国内のワイン需要を振興する個性ある商品や施策が今後の課題となる。
ふりかけ・お茶漬けの素(2024年10月10日号)
ふりかけ・お茶漬けの素市場は物価高による生活防衛のため節約志向が強まる傾向が続き、家庭内食化率や弁当持参率はアップ、価格改定後も相対的にまだ割安感があるため順調にプラス成長している。店頭での米不足は新米が出回って解消されてきたが前年と比べて価格が高いことが懸念材料となるが、1食当たりにするとまだ安価。ふりかけは“食感系”以外、安心感のある比較的ベーシックな新商品が多く、キャラクターのテコ入れが課題。お茶漬けも安定成長、永谷園の「めざまし茶づけ」提案が奏功しているが、今秋はFD(フリーズドライ)米を使用した、お湯を注ぐだけの「カップ茶づけ」を投入、オケージョンの拡大と新規層の獲得を目指す。
スープ(2024年10月10日号)
家庭用スープ市場は味の素社によると23年度が1216億円(消費者購入ベース)、前年比5・1%増で着地、24年度は1252億円、3・0%増の見通し。理研ビタミンが発売した液体濃縮スープ「割るだけスープ」が日本アクセスの「新商品グランプリ」でグランプリを受賞、今までになかった新スタイルのスープとして市場活性化の起爆剤になりそうな勢い。味の素社は「クノールカップスープ」のコミュニケーションを一新、スープの基本価値を改めて訴求する。容器入りスナックスープは好調をキープする見込みで、成長株の電子レンジ対応具入りレトルトスープは存在感が大きくなってきた。ウィズライススープは安定成長を見込む。
洋風ワンサーブスープは今秋、味の素社が「クノールカップスープ」のCMキャラクターを5年ぶりに一新し放映を開始した。ポタージュとオニオンコンソメのCMは初放映。近年、ライフスタイルの変化もあり、家族で一緒(…)
洋風ワンサーブスープは今秋、味の素社が「クノールカップスープ」のCMキャラクターを5年ぶりに一新し放映を開始した。ポタージュとオニオンコンソメのCMは初放映。近年、ライフスタイルの変化もあり、家族で一緒(…)
育児関連(2024年10月7日号)
育児用粉ミルクの国内市場は、4〜8月で前年比微増(金額、物量とも)と推定されており、出生数が毎年5%減ペースで推移する中で好調に推移している。働き方の変化で母乳の機会が減少していることに加え、男性の育児参加が進んだことが背景にある。当面は同様の傾向が続くとみられるが、出生数の減少が続くようだといずれ消費量の減少は避けられない。メーカーでは乳児用液体ミルクや環境対応、利便性の高い商品など付加価値商品に注力している。また1歳ごろからのフォローアップミルクの減少傾向が続いており、新たな役割、価値の訴求で底上げを図りたいところ。
育児用粉ミルクの生産量は1〜7月で5・5%減だが7月が大幅に減少した(…)
育児用粉ミルクの生産量は1〜7月で5・5%減だが7月が大幅に減少した(…)
プレミックス(2024年10月7日号)
家庭用プレミックスは、2021年9月から24年8月にかけて、業界メーカーが、連続5回の値上げで採算是正してきた。マーケットは、全般的に物量面では反動に見舞われているのは否めない。一層の消費喚起が課題。無糖系のお好み焼粉・揚げ物用ミックスや、加糖系のホットケーキミックスなどでの手作りを強力にプッシュする必要がある。秋需向け商品施策は大手製粉系中心に活発で、美味しさをブラッシュアップ、従来からコスパ&タイパのトレンドも訴求。お好み焼系や揚げ物系では、日清製粉ウェルナ、日本製粉、昭和産業などが、店頭での生鮮連動のプロモーション展開。旬の食材を使うメニュー提案型の販促は定番。手作りは、出来立ての味わいが楽しめることが推し。加糖のケーキミックス類は、大手製粉3社と森永製菓などが手軽なホットケーキ中心に、付加価値型にシフト。
【 総数:2031件(76〜90件を表示) 】 前の15件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 次の15件