食料醸界新聞は、毎号、トレンドに合わせた特集・企画をしています。
※スクロールして下さい
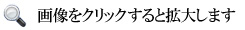
※スクロールして下さい
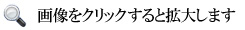
【 総数:2031件(533〜546件を表示) 】 前の14件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 次の14件
ギフト市場(2020年6月8日号)
ギフト総市場は、堅調な右肩上がりを続け、直近で11兆円に迫る有望市場。高齢化などの影響で中元や歳暮などのフォーマルギフトこそ縮小傾向にあるものの、バレンタインやひなまつり、イースター、母の日、ハロウィンといったカジュアルギフト、プレミアムやノベルティー、インセンティブといったセールスプロモーションギフトが伸長し、構成比を高めている。そうした中、今年の中元ギフトだが、大方の予想通り、新型コロナウイルス感染症の影響が色濃く出たものとなっている。昨年中元実績は推定5%減だったが、今年はコロナの影響でさらに悪化し、2ケタ以上減少するとの見方もされている。いまだ感染拡大が警戒され、3密を避ける「新しい生活様式」のもとで、ギフト売り場は全体的に縮小(…)
こだわり食品(2020年6月4日号)
新型コロナウイルスの影響で内食需要が高まっている。2月以降、食品スーパーマーケットの販売実績を見てもその傾向は明らかで、各社軒並み2ケタ増という異常値が続く。また、以前にも増して消費者の健康志向は高まりを見せており、“健康的な食生活”が重要な要素となってきた。こだわり食品群についても、健康を特徴とした商品は数多くある。内食需要と健康志向のさらなる高まりは、こだわり食品群にとっても追い風とも言え、改めて情報発信を強化していきたい局面にあると言えそうだ。
“こだわり食品”の定義はさまざまだが「原料」「製法」「容器」などに“独自性を持たせた商品”というのが一般的な認識である。量販店では“バイヤーの(…)
“こだわり食品”の定義はさまざまだが「原料」「製法」「容器」などに“独自性を持たせた商品”というのが一般的な認識である。量販店では“バイヤーの(…)
スーパーの挑戦(2020年6月1日号)
新型コロナウイルスの影響で、スーパーマーケットの売上高は高伸長を続けている。こうしたなかで首都圏でも緊急事態宣言が解除され、大型商業施設や外食店などの営業再開が本格化している。今後は外食需要の回復や生活者の価格志向が高まることが想定され、スーパーマーケットを取り巻く環境も変化する。価格競争の激化が懸念されるなか、新型コロナにより変化した食市場にむけた新たな提案を、製配販が連携して実施していくことが求められる。
首都圏のスーパーマーケット企業では、引き続き売り上げが高止まりする状況が続いている。サミットでは、新型コロナの影響で開業が1カ月以上遅れていた「桜木町コレットマーレ店」(横浜市)を5月20日にオープン。内食回(…)
首都圏のスーパーマーケット企業では、引き続き売り上げが高止まりする状況が続いている。サミットでは、新型コロナの影響で開業が1カ月以上遅れていた「桜木町コレットマーレ店」(横浜市)を5月20日にオープン。内食回(…)
ハム・ソーセージ(2020年5月28日号)
ハム・ソーセージ各社は今年も引き続き、主力・重点・中心ブランドの一層の強化を継続するとともに、健康や簡便、即食、時短、電子レンジ対応といった様々な消費者ニーズに対応できる商品の開発・拡充を進めている。そうした中、新型コロナウイルス感染症が発生。蔓延を防止する取り組みの一環で全国で外出を自粛する動きが見られ、在宅率も高まり、その結果、巣ごもりを基調とする生活スタイルと内食需要が生まれた。この影響を受け、ハム・ソーセージ、調理加工品、食肉も家庭用を中心に売れ行きが増大。従前より注力してきた常温食品などにも数多くの引き合いが寄せられており、巣ごもり消費長期化で、各社製造拠点のフル稼働で対応。コロナにより、プラントベースミート(PBM(…)
即席めん市場(2020年5月28日号)
新型コロナウイルスの影響により即席めんの需要が増大し2月下旬以降、主要メーカーは定番商品に生産品目を集中し、増産態勢により安定供給を続ける。ただ20年度(4〜3月)の市場は予測が難しい。新商品の発売延期や絞り込み、プロモーション計画の見直しなども発生しているが、夏に向けては焼そば・汁なし麺、冷やし麺など例年通り投入する予定。引き続き主要ブランドの価値向上と売上拡大を目指し、新しい切り口で新規顧客層の獲得策も推進する。
日本即席食品工業協会によると3月のJAS受検数量は前年同月比で11・1%増(非JAS含むドライ合計19・3%増)、内訳は袋めん18・2%増(27・9%増)、カップめん8・1%増(15・5%増)。この高水準の伸びは4月も続き、生産品目の集約と増産態勢により即席めん計で14・0%増と前月より2・9ポイントアップ、袋めんは16・4%(…)
日本即席食品工業協会によると3月のJAS受検数量は前年同月比で11・1%増(非JAS含むドライ合計19・3%増)、内訳は袋めん18・2%増(27・9%増)、カップめん8・1%増(15・5%増)。この高水準の伸びは4月も続き、生産品目の集約と増産態勢により即席めん計で14・0%増と前月より2・9ポイントアップ、袋めんは16・4%(…)
飲料業界(2020年5月25日号)
飲料業界は、1〜2月は順調だったが、新型コロナの影響を受け3月の市場はメーカー出荷(数量ベース)で前年同月比95%、4月は約80%となり、その後2ケタ減が続いている。仕事や行楽など日常生活の幅広い場面に浸透していただけに、人の移動、経済活動が制限され、飲料の需要が大幅に減少した。天然水をはじめとして食品スーパーでの大型PET販売や、通販利用が急増するなど、在宅時間の増加によって伸びた需要もある。今後、自粛緩和され、飲料の最需要期である夏に向かう。春に抑制していたマーケティングや販促投資などを本格化する。前年7月は大幅減だったため、今年の夏は前年を上回るのが確実だが、コロナの影響をどこまで取り戻すことができるか。
チェーンストア(2020年5月21日号)
新型コロナの影響を受ける“ウイズ・コロナ”の食市場では、外食・中食から内食・家庭内調理への回帰が進むとともに、ネット通販や宅配の利用が増加している。多くの業界関係者は、新型コロナ終息後の“アフター・コロナ”の食市場でも、こうした傾向が続くと想定している。これまでもチェーンストア企業では、生鮮強化やミールキットの開発、ネット通販や宅配への取り組みなどを進めてきた。“ウイズ・コロナ”“アフター・コロナ”の食市場でも、これらの施策が重要となるため、各社ともそれぞれの取り組みを加速させる方針だ。一方、有力企業の20年2月期業績(8面参照)をみると、厳しい状況が続いていることがわかる。さらに、今後は景気後退から価格志向が強まるとみられ、これにも対応し(…)
CVS(2020年5月21日号)
新型コロナウイルス感染症の影響による緊急事態宣言下でも、コンビニエンスストアは可能な範囲で通常営業を継続。食料品など生活必需品を販売する店舗として、インフラの役割を果たす。チェーン本部は必要な物資の支給や売上減となった店舗への支援を行う。19年4月に各社が発表した「行動計画」は進捗を報告し、加盟店支援を強化している。21年2月期の新たな取り組みとして、アプリ、デジタル技術を活用した販促を強化する。ミニストップは新規事業の専門店を展開し、今後の収益化を目指す。
新型コロナウイルス感染症対策のため、4月7日に緊急事態宣言が行われた。5月4日に同月31日までの延長が行われたが、新規感染者数減少などを受(…)
新型コロナウイルス感染症対策のため、4月7日に緊急事態宣言が行われた。5月4日に同月31日までの延長が行われたが、新規感染者数減少などを受(…)
甲類焼酎(2020年5月18日号)
甲類焼酎は、レモンサワーブームを追い風に若い世代の需要開拓が進む。新型コロナウイルスの感染拡大で、業務用市場は他酒類と同様に厳しいが、巣ごもり消費の家庭用はレモンサワーをはじめとするベーススピリッツとしての需要拡大で、とくに大容量の定番商品中心に伸長傾向にあるとみられている。居酒屋などでレモンサワーを飲んでいた人が、家飲みで甲類焼酎に選択肢を広げることが期待される局面である。
日本蒸留酒酒造組合は、何にでも合わせやすく、自由に割ることができる焼酎甲類を広く普及させるために、DJ KOOさんをアイコンに起用した新CM「DJ KOO類、誕生」篇を4月6日からユーチューブで公開。焼酎甲類ミックス(…)
日本蒸留酒酒造組合は、何にでも合わせやすく、自由に割ることができる焼酎甲類を広く普及させるために、DJ KOOさんをアイコンに起用した新CM「DJ KOO類、誕生」篇を4月6日からユーチューブで公開。焼酎甲類ミックス(…)
焼肉のたれ市場(2020年5月18日号)
新型コロナウイルス感染が拡大するなかで、食市場が大きく変化。外食や中食から、内食、そして家庭内調理へのシフトが進んでいる。そのなかで焼肉のたれ市場では、レジャーとして楽しむBBQ需要は大きく減少しているが、スーパーマーケットでの畜産売り上げは大幅に拡大しており、家庭内で家族で囲む食卓での焼肉需要は大きく伸長している。さらに、家庭内調理が増加するなかで、汎用性の高い調味料である焼肉のたれが活躍する場面が増えていると考えられる。ただ、スーパーマーケットは売り上げが高止まりや感染防止対策の取り組みなどに時間と人手をとられ、価値提案や売り場提案がほとんどできない状況にある。こうした新型コロナ影響下の“ウイズ・コロナ”、さらには終息後の“アフター(…)
乾麺(2020年5月14日号)
乾麺の今年春夏需要期商戦は、近年にない、異例づくしの展開となっている。新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため在宅率が高まったことによる内食需要の増大などが要因。保存・備蓄性がある乾麺への需要は、商戦入り前の2月から例年にないほど高まり、緊急事態宣言の発出でますます強まる内食傾向を背景に、ここまで継続している。引き合いは特に家庭用小袋商品に集中。手延麺は前年を超える出荷ペースで、機械麺は全社挙げた増産態勢。一方で、春季新商品販促に影響が及び、夏季最盛期に向けた商品供給に不安が出るなど、コロナショックも見受けられる。中元ギフト商戦への影響も必至との見方。巣ごもり消費を背景とした例年より早い実需発生の中でシーズンインした今年の乾麺商戦。(…)
めんつゆ(2020年5月14日号)
今シーズンのめんつゆ市場は“予測不能”というのが関係者の一致した見解だろう。新型コロナウイルス感染拡大による不要不急の外出自粛要請、緊急事態宣言発令により在宅率の高まり、巣ごもり消費により乾麺が一時店頭で品薄になり、めんつゆ類も同時に売れた。家庭内での調理機会の増加で濃縮つゆの使用頻度もアップ、改めて麺メニュー以外の用途訴求が大事になってくる。使用機会が増えれば減塩、糖質オフなどのヘルシー系や、こだわりの原料を使用した付加価値タイプの購入率も高まってくる見通し。
盛夏に向けて主要メーカーは増産態勢に入ろうとしていた時期に、例年を大幅に上回る需要拡大により、一部メーカーでは供給がタイトになってしまっ(…)
盛夏に向けて主要メーカーは増産態勢に入ろうとしていた時期に、例年を大幅に上回る需要拡大により、一部メーカーでは供給がタイトになってしまっ(…)
ウイスキー市場(2020年5月11日号)
好調な拡大が続くウイスキー市場は、新型コロナの感染拡大によって、先行きの見通しが立たない状況になっている。全国に対象を広げた緊急事態宣言が、当初の5月6日までから31日まで延長され、飲食店などの休業が継続。とりわけウイスキーの需要が多いBARをはじめとするナイトマーケットは、早い段階から自粛が強く求められ、消費がストップした状況が続いている。緊急事態宣言以降は、居酒屋などで人気のハイボールの樽詰め供給にも大きな打撃となり、現時点では「コロナ禍の早期の収束を願うのみと言うしかない」(メーカー)。一方で、巣ごもり消費で家飲み需要が増えているのは追い風。2019年のウイスキー課税数量は前年比108・6%の19万3934kl(約2309万ケース、8・4l換算)で、11(…)
惣菜市場(2020年5月11日号)
新型コロナウイルス感染拡大が惣菜市場に大きな影響を及ぼしている。女性の社会進出や家庭内調理の減少などから、スーパーマーケットの惣菜売り場で販売するフレッシュ惣菜の市場は、これまで拡大を続けてきた。ところが3月以降は、新型コロナの影響により、前年割れに陥っている。代わってコロナ禍の食卓を支えているのがロングライフ(LL)惣菜で、販売が一気に拡大。多くの消費者が、製造技術の進化により品質が向上しているLL惣菜の価値を実感することとなった。こうした変化が、新型コロナ終息後の“アフター・コロナ”の惣菜市場に、どのような影響をもたらすのか、今後の動向を注視する必要がある。
全国スーパーマーケット協会、日本スーパーマーケット協会、オール日(…)
全国スーパーマーケット協会、日本スーパーマーケット協会、オール日(…)
はちみつ市場(2020年5月7日号)
2019年の蜂蜜の輸入量1位は中国、2位アルゼンチン、3位カナダで、前年と変わらない順位となったが、このところ中国産の構成比は漸減傾向が続いている。その一方で、カナダやアルゼンチン、ハンガリー産が増加するなど、ニーズが多様化してきた。19年の蜂蜜市場は前年並みで、特段大きな伸びもなかったものの順調に推移。今年は、2月下旬から新型コロナウイルス禍が勃発。テレビ報道の影響もあって、需要は一時大きく跳ね上がり、高額品のマヌカハニーやプロポリスにまで波及した。
2019年(1〜12月)の輸入量は、約4万4788t、前年比100・6%。国別では、第1位の中国産は約3万518t(96・8%)で、全体の約7割を占める。構成(…)
2019年(1〜12月)の輸入量は、約4万4788t、前年比100・6%。国別では、第1位の中国産は約3万518t(96・8%)で、全体の約7割を占める。構成(…)
【 総数:2031件(571〜585件を表示) 】 前の15件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 次の15件


















